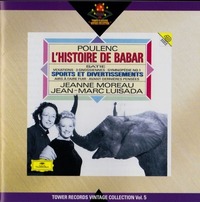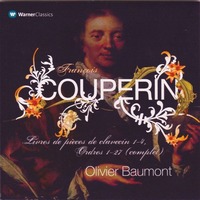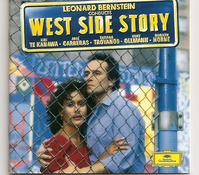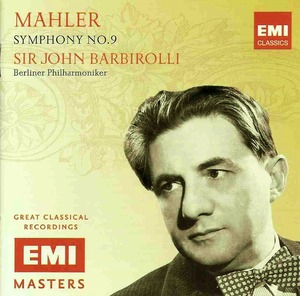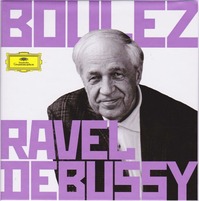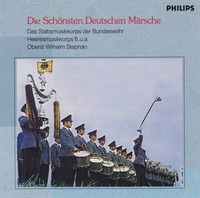電車のシートはロングシート(お見合いシート)だったので、乗り込んだ私はさっそく靴を脱いで窓の方を向いて席にお座りした、かったけど、そんなことをしたら拘留されてしまうかもしれないので、ドアの近くに立って外を眺めることにした。
ニュースで流れるのは建物の正面の映像ばかりだが、車窓から見えたのは横から。三角屋根の姿が見えたが、感激のあまり涙するには通過するのが速すぎた。じっと見ても感激しないだろうけど。
ほかに、学園を取り囲むように公園や幼稚園、大阪音楽大、私立庄内体育館などが建っている。
だが、ときおり悪意のないウソをつく。いや、ウソというのは言い過ぎだ。単なる勘違いを思い込んでいるのだろう。
ところで、上の写真のたこ焼き屋さんは何と読むのだろう。