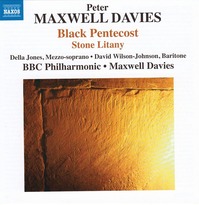あっ、寿司&そばのランチセットと同じか
あっ、寿司&そばのランチセットと同じか
いよいよ大晦日である。
今日の夜は、北海道のしきたりにしたがって、寿司とそばを食べなければならない。
でも考えてみれば、これって決して珍しいことではない。
“寿司+そば”セットって、たとえば音更町の木野の“蔵”(ローカルな話ですいません)とかで昼に食べることもあるからだ。
寿司じゃないが、何日か前には“一福”というよもぎそばの店で、豚丼+そばセットを頼んで、しかも無謀にもそばを大盛りにしたせいで途中で飽きて来たものの完食してしまったし。
今日はレハール(Franz Lehar 1870-1948 オーストリア)のオペレッタ「メリー・ウィドウ(Die lustige Witwe/The merry widow)」(1905)。
初演されたのはいまから110年前の12月30日。
そして今日紹介する録音は、いまから5年前の2010年の大晦日に行なわれたコンサートのライヴである。
“メリー・ウィドウ”は“陽気な未亡人”の意味。
架空の国・ポンテヴェドロの若い未亡人が巨額の遺産を相続してパリにやって来るのだが、資産が国外に流出する心配をするポンテヴェドロ(モンテネグロをもじっている)の大使や、未亡人に言い寄る男たちの騒動を描いた喜劇。台本は、H.メイヤックの喜劇「大使の随員」から、V.レオンとL.シュタインが作った。3幕からなる。
今日取り上げる“ニュー・イヤーズ・イヴ”コンサートのCD(抜粋盤)は、ティーレマン指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団による演奏。
歌手は、未亡人役(S)がフレミング、ダニロ(T)がモルトマン他。
しつこいようだが2010年12月31日ライヴ。グラモフォン。
このオペレッタのスコアはヒトラーに贈られたことだし……
ところで、「メリー・ウィドウ」でダニロが登場する場面の歌「おお祖国よ…マクシムへ行ったが(O Vaterland … Da geh' ich zu Maxim)」(このCDでは第3トラック)のなかのメロディーを、ショスタコーヴィチが交響曲第7番の第1楽章で用いていると言われる。戦争の主題である。
S.ヴォルコフの「ショスタコーヴィチの証言」(中央公論社)の“訳者あとがき”で水野忠夫氏はこう書いている。
柴田(南雄)氏は「ショスタコーヴィチの『回想録』」(「海」1980年6月号)のなかで、本書の第7交響曲「レニングラード」についての、従来の定説を否定するショスタコーヴィチの記述について、「あのラヴェルの『ボレロ』の骨組が見え見えの第1楽章が、迫り来る戦争の描写とは滑稽だと心ある聴き手なら誰でも思っていた」と書き、「戦争の主題」のパセージをレハールのオペレッタ「メリー・ウイドー」の引用とみなして、「公使秘書ダニロというのが第1幕で歌う『それで私はマキシムに行く、そこはとても気楽なのさ』の旋律そのものが『戦争の主題』に化けたのである。しかも、そのダニロの歌のリフレーンが『彼女たちは親愛なる祖国を忘れさせてくれるのさ!』であるのにはまったく恐れ入る。もし、党や作曲家委員会の幹部がそれを嗅ぎつけていたら、彼の運命はどうなっていたであろう」と書いておられた。 マキシムというのも何か意味ありげである。
マキシムというのも何か意味ありげである。
ショスタコーヴィチの息子の名はマキシムだから。
ただ、この「ダニロの歌」、「おぉっ!これはショスタコの“戦争の主題”だ!」とモロだしのように明確かというとそこは微妙。ぼぅーっと無防備で聴いていると、気づき損ねるくらいだ(少なくとも私には)。
そして、確かに良く似ているが偶然とも考えられなくもない。たぶん偶然じゃないだろうけど。
それは天のショスタコのみが知る永遠の謎だろう。
大晦日イヴの昨日、私が乗った上り、つまり札幌行きの特急はとてもすいていた。
いつもより1両多い7両編成だったが車内はこんな感じ。いえいえ、シートから頭が見えないだけで、幼児がびっしり座っているというわけでは決してない。
途中の駅でもトマムで少し乗って来たくらいだった。
でも、この列車の折り返しとなる下りは満席もしくはそれに近いのだろう。 札幌駅に着き、安全管理役の駅員のようあたりを見渡すと、いくつかのホームの函館や帯広・釧路方面の特急の自由席車両の停車位置には、列車が入線するまでけっこう時間があるというのにかなりの列ができていた。
札幌駅に着き、安全管理役の駅員のようあたりを見渡すと、いくつかのホームの函館や帯広・釧路方面の特急の自由席車両の停車位置には、列車が入線するまでけっこう時間があるというのにかなりの列ができていた。
さて、2010年の大晦日だが、私は年末ジャンボ宝くじに当たらなかった。
今夜はどうだろう?一応バラで10枚は買ったのだが……
それはともかく、今年1年ありがとうございました。
明日からもよろしくお願いいたします。
2015/12
 いまの若いもんには象印賞なんてわかるまい
いまの若いもんには象印賞なんてわかるまい
殊勲敢闘技能となぜか国技の三賞のように今年聴いて印象に残ったディスクを紹介したが、今年北の湖亡くなったこととは関係ない。
で今日は番外編。あえて名づけるなら(名づけなくてもいいんだけど)象印賞。
苦労して入手したボーモンによるクープランのクラヴサン曲集全集。
バッハやヘンデルとはまた違った音楽であり、また意味深なタイトルが面白い。
ヤルヴィによるショスタコーヴィチの「森の歌」はすばらしかった。
出会えてよかった。こういう演奏をしてくれてありがとうと言いたくなる出来だ。
また、ポルポラのアリア集を1枚買ったが、最初に収録されている曲でいきなり歓喜させられてしまった。いやなことなど吹っ飛びそうなノリの音楽である。
ところでクラフトが指揮したシェーンベルク編のブラームスのピアノ四重奏曲のCDを買ったのは年明けすぐのことだった。
そのクラフトが去る11月10日に亡くなったと“レコード芸術”に載っていた。
クラフトを偲んで1曲。
追悼向きの音楽ではないが、彼がロンドン交響楽団を指揮したストラヴィンスキー(Igor Stravinsky 1882-1971 ロシア→アメリカ)のバレエ「妖精の口づけ(La baiser de la fee)」(1928/改訂1950)。
チャイコフスキーの曲を素材とするこのチャーミングな音楽を、得意げな(のように聴こえる)演奏でクラフトを
送りたい(このディスク(組曲版)に関する過去記事はこちら)。
1995年録音。ナクソス。
さ、今日はこのあとスーパーとかちに乗って札幌へ向かう。
わ~い、年末年始のお休みだぁ~い!
って、その前にJRの運行にトラブルがありませんように。
先日函館本線の旭川と深川の間でトンネル火災が起ったのをニュースで観た方も多いだろう。
えっ?旭川なのになぜ函館本線かって?
とにかく、函館-長万部-倶知安-小樽-札幌-岩見沢-旭川は函館本線。
長万部から苫小牧周りで札幌を結ぶのが室蘭本線と千歳線なわけ。
年末の書き入れ時に運休せざるを得ないというのは、JR北海道を気の毒に思わなくもないが、これも安全管理が不十分だったってことになっちゃうのだろう。
でもなぁ、弱り目に祟り目……って感じで、いろいろな構造的な問題があるにせよ、同時にどうしようもない苦悩もあるような気がして、ただ責めるだけの問題じゃ済まされない思いがする。
 ジャケット写真が音楽を表している
ジャケット写真が音楽を表している
この曲も“ぶっちさん”から推薦コメントをいただいたもの。
P.M.デイヴィス(Peter Maxwell Davies 1934- イギリス)の歌劇「復活(Resurrection)」Op.129(1987)である。
そのときの記事に書いたように、ずっとずっと探し求めていたデイヴィスの「石の連禱(Stone litany)」(1973)のCDを発見しその喜びと戸惑いについて書いた記事を読んだぶっちさんが、それならこれもいかがと紹介してくれたのだった。
クラシック音楽以外のジャンルについてとんと疎いので的外れなことを書いているかもしれないが、ロックとクラシックが融合したような曲。
ぶっ飛び度は満点だ。
いわゆるクラシック・クラシックしていない歌唱も、私には新鮮。
クラシック嫌いの人でもお気に召していただけるに違いない可能性を秘めているかもしれないような気がしないでもない。
「石の連禱」は“通奏高音”のように響き続けるグラスハープの音が美しい。
甘いだけではない。刺激も十分
今年新たに出会った曲で、これまたすばらしかったのがシュニトケの映画音楽。
8月24日、29日、9月4日、11日と4回にわたって取り上げたが、そのなかでもJ.シュトラウスのメロディとオリジナルのメロディが織りなす「ワルツ」(9月4日の記事で紹介)にはすっかりやられてしまった。
私はこれらの作品群に技能賞を与えたい。
このCDの存在は“ぶっちさん”が教えてくれたのだが、ぶっちさんには深く感謝いたしたい(言葉だけだけど)。
耳に心地よい(といっても、あちこちに毒っ気があるが)親しみやすい音楽は、晩年の不機嫌そうなシュニトケの音楽とはずいぶんと違う。
と思うと、勝手ながら自分の好みの話だけど、シュニトケって晩年は気難しい変な方向に行っちゃったような気がしないでもない。
この滅茶苦茶さもある意味技能?
今年は、意味不明のひらがなが並んでいる謎めいたスパムメールをこことここでご紹介した。
最後にもひとつ取り上げておこう(もひとつ届いていたので)。
酒井〇子薬漬けのクラブ通いで遂に全裸公開☆
限定動画「**********@********」様へ
酒井◇子さんが、薬物漬けのクラブ通いで全裸になってしまった映像!つはちつれむろも!つはちつれむろもつはちつれむろも
ちょっとリアル過ぎて怖いかもしれません!つはちつれむろも!つはちつれむろもつはちつれむろも
誰か、なぜこんな変にひらがなが並んでいるのか、その心を教えてはくれまいか?
いやゆるウマヘタの世界?
昨年は伊福部昭の生誕100周年だったが、今年に入ってもいくつかのCDがリリースされた。
100周年だった2014年に行われたコンサートのライヴCDである。
そのなかで敢闘賞を授与したいのが“伊福部昭 百年紀Vol.3”の「キングコング対ゴジラ」(ブログ記事は→こちら)。
(そろってしまわないような)練習の賜物か、あるいはマジに乱れているのかわからないところがあるが、原住島民の歌らしいワイルドさと微妙なズレがすばらしい効果をあげている。
合唱は歌に陶酔しているようで、これまた魔人に畏怖し崇めているうちに興奮のるつぼみたいに自分たちもイッチャッテるっぽいのが、これまたみごと。
にしても“太鼓”の乱れ打ちを聴くと伊福部ってミニマルも盛り込んだ?と思ってしまう。
いや、こうなるとマキシマムか?
長女も70歳になりました
そういえば、24日の北海道新聞朝刊に伊福部玲さんが載っていた。
記事はこれ。
偶然NEW FACE目撃
昨日偶然にも新塗装のスーパーとかちを目にすることができた。
すっきりしてなかなかよろしい。
JRでは“スーとか”の車両を順次この塗装に更新していくそうだ。
1年を振り返る
といっても、あのとき地下鉄でお年寄りに席を譲るべきだったとか、凍った道路を渡ったとき転ばないように杖を携えておけばよかったとかという反省ではない。
そんなこと毎日、それも何回も/日あることなので、いちいち振り返ってられない。
ここで振り返るのは今年聴いて、そのなかでも顎が外れるくらい衝撃を受けてしまった、というとオーバーかもしれないが、印象に残った曲についてである。
今日は最高栄誉賞を授与したい曲。
ゴードンの「ディストピア」と「ベートーヴェンの交響曲第7番の再構築」である(掲載記事はこちらとこちら)。
買ったレコ芸に偶然にも……
そうそう、先日“くま”さんのブログ“知られざる佳曲”を読んでいたら、レコード芸術の12月号を買うべきか見送るべきかという悩みが書かれていた。
まったく私と同じ悩みである。そしてそのあとくまさんは結果的に購入したという。
私もそれに習ってというわけではないが、かすかな焦燥感を抱きながら本屋に向かった。そして表紙を眺めるだけじゃ満足できず買った。というのも、今回は付録で“レコードイヤーブック”がついているからである。
そのレコ芸の12月号にこのゴードンのCDが紹介されているではないか!
“海外盤REVIEW”のコーナーで谷口昭弘氏はこう書いている。
……《ディストピア》は、ロサンジェルスの喧騒を、アンタイルの《バレエ・メカニック》のような変拍子、ピッコロのピコピコ・オスティナート、エンジン音を模倣するトロンボーンのグリッサンドで描く。……《ベートーヴェン交響曲第7番の再構築》は、例えば第1部が原曲の冒頭の2つの和音を繰り返し、弦のグリッサンドがそこに絡むというように、各楽章の素材による破天荒な内容だ。……どちらもゴードンを恥じらいを捨てた1人の作曲家として突き放すか、生暖かく見るか、イマドキのゲンダイ音楽として楽しむかという選択肢になりそうだ。
私は大いに楽しめた。突放禁止じゃあるまいし、なぜ突き放すことなんてできるというのか?
吉本新喜劇を観ているような、そんな気分にさせてもらった(生暖かく見るってどういうことなのだろう?)。
ゲンダイ音楽といってもこの2曲はまったく無機質ではない。むしろ人間臭さプンプンである。
それがイマドキのゲンダイ音楽ってことなのかもしれない。
騙されたと思って聴いてみるべし!
そして結果として騙されたと痛感しても私に怒りをぶつけることのないように!
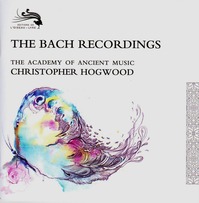 バタークリームが好き!
バタークリームが好き!
今日こそがクリスマス当日である(ちなみに、急用や訴えごとに良い日とされる“先勝”)。
ところでみなさんはこのたびはケーキを食べただろうか?
キョウビ、ケーキのクリームといえば生クリームが大勢を占めるのだろうが、私はバタークリームのほうが好きである。少なくとも植物性脂肪のクリームもどきよりはるかに美味い。純動物性のクリームも美味いが、本物のバタークリームの美味さはもっと美味い(あくまで個人の感想です)
が、コンニチなかなかバタークリームのケーキが見当たらないのが残念である(帯広市郊外の大正という街にある“あくつ”という菓子店のバタークリームを使ったヘーゼルナッツロールは秀逸である!)。
バターをコーヒーに浮かせたことあります?
ところで先ごろ新聞だったかネットだったか忘れたが、バターコーヒーが地味にブームだと書いてあった。
バターコーヒーというのはそのものズバリ、フレッシュクリームの代わりにバターを入れるのである。
保育社のカラーブックスという驚くべき良書のシリーズがかつてあった。
そのなかの1冊「コーヒー入門」。
この本は1971年に刊行されたが、そこにはすでにバターコーヒーが紹介されていた。
私はむかし一時期コーヒーを淹れ、そして飲むことに凝っていて、この本を持っていたのだった。
危険な習慣性あり?
バッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750 ドイツ)の世俗カンタータ「そっと黙って、おしゃべりなさるな(Schweight Stille, plaudert nicht)」BWV.211(1734頃-35)。通称「コーヒー・カンタータ(Kaffee-Kantate)」と呼ばれている。
10曲からなるが、詞は第1~8曲がC.F.ピカンダー、残り2曲はバッハ自身による可能性もあると言われている。
登場人物はシュレンドリアン(バス)とその娘リースヒェン(ソプラノ)。テノールが語り手を担う。
コーヒーを飲むのを止めないリースヒェン。シュレンドリアンはなんとか止めさせようと、止めるかわりに恋人を探して来てあげると言う。娘もそれならと止める決意をし、父親は婿探しに出かける。しかしリースヒェンは心の中で、コーヒーを飲ませてくれる人とじゃないと結婚しないと決める。
みんなが飲むのを止められないのに、娘にコーヒーを止めさせられることはできないというオチで終わる。
当時はコーヒーが大ブームだったらしく、それを皮肉ったものだ。
いまなら老いも若きもあらゆる場面でコーヒーを当たり前のように飲んでいるが、バッハの時代ならもしかすると危険な習慣性のある飲料と考えられていたのかもしれない。
カークビーのソプラノ、トーマスのバス、カヴィ=クランプのテノール、ホグウッド指揮アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックによる演奏で。
1986年録音。オワゾリール。
私の記憶に間違いがなければ「コーヒー入門」でも「コーヒー・カンタータ」が紹介されていたと思う。
たぶんそれで、私はこの曲の存在を知ったのだった。
でも、いまバターコーヒーが地味に流行ってるってホントかね?
まあ、いずれにしても、メリー・クリスマス!
 サンタは赤い。赤いはくーち!
サンタは赤い。赤いはくーち!
12月24日である。
今日この日は、お気づきの通り“赤口(しゃっこう/しゃっく)”だ。
万事において大凶の日である。でも正午だけは吉だという。
ということは、気を緩めて「♪ジングルベールっ!」って鼻歌を歌っている場合ではない。
でも、昼のNHKニュースの始まりと同時に七面鳥を食べると良いことがあるかもしれない。
ところで「ジングルベル(Jingle Bells)」はイギリスの牧師ピエールポント(James Pierpont 1822-93)が作詞作曲した歌。もともとはクリスマス用に書いた曲ではないそうだ。
クラシック音楽作品にも鈴を用いた曲は少なくないが、私の頭にまず最初に浮かぶのはやはりマーラー(Gustav Mahler 1860-1911 オーストリア)の交響曲第4番ト長調(1892,1899-1900/改訂1901-10)である。
メルヘンのようだが実は怖い世界……。交響曲世界における赤口である(か?)。
今日はガッティの演奏にしておこう。
オーケストラはロイヤル・フィル、ソプラノ独唱はツィザーク。で、感想はこちら。
前世紀末である1999年の録音。BMG。
いい歳したおっさんが、ホームで萌える
昨日書いたPENTAXの一眼レフカメラ。私の自分へのクリスマス・プレゼントである(ということに今日位置づけた)。
旭光学という会社がなくなりPENTAXブランドがリコーへ移っても、やっぱりペンタックスが好きだ。
そして一眼レフのあのシャッターを押した感覚!
カシャッ!カシャッ!カシャッ!
久々の“これぞシャッター!”っていう指先体験に私は萌えた!(って、ここだけ読むと、いかがわしいマッサージ体験談か三和シャッターの推薦文みたいだ)。
で、青春時代を思い出し、帯広に戻る際、スーツ姿にもかかわらず札幌駅のホームで列車を撮ってみた。
何?たいした写真じゃないって?
そう言うな、まだ慣れてないんだから……
にしても、フィルム代と現像代のことをまったく考えなくていいというのは実に気が楽だ。まっ、一眼レフに限ったことじゃなく、デジカメすべてに言えることだけど。
そういえば、MEスーパーを買ってすぐのころ、札幌駅(もちろん昔の)で列車を撮っていたら見知らぬおじさんが「列車と一緒のところを撮ってあげよう」と声をかけてきたことがあった。
「いえ、いいです」と私ははにかんで答えたが、あの時は内心、カメラを持ち逃げされたらたまったもんじゃないと警戒をしていたのだった。
 ポジティブに生きようぜ
ポジティブに生きようぜ
自宅で本棚を整理していたら、20年ぐらい前まで使っていたスライド・ファイルが出てきた。
スライド・ファイルとは上下左右にスライドする便利な(?)ファイルのことではない(そもそもそういうものがどんなものか想像不可である)。
ポジ、つまりリバーサル・フィルムで撮影したスライド写真を保管するファイルである(その反対がネガフィルムである)。
学生時代、私は植物写真を撮り続けていた。
そして、私の愛機は絞り優先撮影のペンタックスのMEスーパーであった。
フィルムはコダックのリバーサル・フィルムであるコダクローム(ASA64)。もう少し感度が欲しいときは同じくコダックのエクタクロームのASA200のものを使った。
コダック、特にコダクロームにこだわったのは、ペンタックスのレンズにはコダックの方がフジクローム(富士フィルム)より発色が自然だと感じたことと、ASA64という低感度の方が大伸ばし(スライド映写など)したときに画質が有利と思ったからだ。接写で絞り込むためシャッタースピードが遅くなり苦労したけど……
MEスーパーは20年ほど前まで使っていたのだがフィルムの巻き上げレバーが空回りするようになり、また撮るシーンも家族のスナップ写真が中心となり、加えて子どもの写真をスライドにするはずもなくネガフィルムばかり使うようになったので、もうコンパクトカメラで十分だと思いMEスーパーはしまわれたままになった。
が、5年ほど前にオークションに出品してみた。もちろんレバーが空回りすることは明記して。
1万円ほどで落札された。落札者の落札履歴からすると中古カメラ店のようで、きっと修理して中古市場で売ったのだろう。でも、きっと売れたに違いない。あのカメラは良いカメラだった。
札幌駅の手荷物一時預かり所でバイトしてお金を貯めて買ったのだが、キャノンでもオリンパスでもなく(ニコンは高くて手が届かなかった)、どちらかといえば地味な存在のペンタックスにしたのは(めったに会わない)叔父の勧めだった。
その叔父はカメラ好き、写真好きだそうで(そのときまでちっとも知らなかったし、それ以降も叔父の撮った写真を見たことがない。そしてもうその叔父は他界した)、ペンタックスのレンズはすばらしいと賞賛していた。
ご存じのように今使っているオリンパスのコンパクトデジカメに、私は不満がある。
画像がいまひとつ締まらない。ピントが甘いのだ。
コンデジだからしょうがないといえばしょうがないのだが、その前に使っていたニコンのコンデジはピシッと決まってくれた。そのニコンの製品のおよそ3分の1の1万円で買えたから、もともと能力は低いのかもしれない(画素数やセンサー、画質の選択などいろんな厄介な事情が複雑に絡み合っているとは思うが)。
やっぱりペンタが好き!
先日札幌の某大型カメラ店“ヨドックカメラ”(仮名)で何気なしにカメラを見てみたら、私を引きつけるカメラがあった。
ペンタックスのK-S1。やっぱり私はペンタックスが好きなのだ。
価格は2本のズームレンズがついたセットで54,000円ほどである。
5万超えか……。でも一眼レフがレンズが2本ついてこの金額で買えるのだから安いことは安い。
一目ぼれしたものの、しかし衝動買いするのを何とか思いとどまった。
その数日後に東京に出張した。
空いた時間があったのでヨドックの某店舗に寄ってみた。
なんとK-S1のあのWズームキットが“お値下げしました”と44,000円(税別)ほどで売っているではないか!
やっぱ東京は安いのね。でもここでは買えないし、妻の許認可も下りてないし……
でも、そのあとネットでヨドックの価格を見ると、全国送料無料で同じ価格で出ている。しかも在庫がある店舗に札幌店も入っている。ということは、44,000円で札幌でも買える。そう判断して間違いない。
妻に「前回よりも1万円も下がったので、アタシはここで買わないと一生後悔するような気がする」と訴え許可を得、先週の札幌出張の際、早めに着くようにして出発し、会議が始まる前にヨドックに寄った。 店頭の価格変更が追いついていない?
店頭の価格変更が追いついていない?
が……、価格は54,000円ほど(税別)。つまり最初に見たときと変わりない。こちらは“お値下げしました”じゃないのだ。
これなら同じヨドックのネットショップで買った方が1万円も安いことになる。
でも、店員さんに尋ねてみた。
プリントアウトしてきたヨドックのネットショップのページを示しながら、「これって、ヨドックさんのネットショップでは44,000円ですけど、こちらではこの価格のままなんでしょうか?」。
さらに「もし合わせてくれるなら購入したいと思うのですが」と大胆なことを言ってしまった。
「ホントですか?ありがとうございます」とまずはお礼の言葉で私の気持ちを高揚させた店員さんはプリントアウトされたものを確認し「ちょっとお待ちください」と言って、奥に引っ込み、2分後に戻って来た。
「ネットの値段と同じで大丈夫です」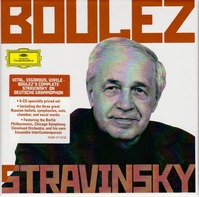 ということで、お互い笑顔で(支払いのことを考えるとやや憂うつではあるが)商談が成立した。
ということで、お互い笑顔で(支払いのことを考えるとやや憂うつではあるが)商談が成立した。
でも、東京の店舗やネットでの価格を知っていたからこそこのように尋ね、そして値引きしてもらえたが、そうじゃない人は54,000円で買っちゃうってことか……。なんか気の毒。それとも買うか買わないか迷っている状態でお値引作戦にでるのかな?
もしかすると自分も店頭価格そのままで、もしかしてもっと安くなるかもしれない可能性を知らないで高いまま買ってしまっていることもあるかもしれないな……
と、この話はいったんここで中断して、今日取り上げる作品は、印象主義音楽のような浮遊感のあるストラヴィンスキー(Igor Stravinsky 1882-1971 ロシア→アメリカ)の「ヴェルレーヌによる2つの詩(2 Songs of Paul Verlaine)」Op.9(1910)。
バリトンを独唱とする歌曲で、第1曲は「大いなる憂うつな眠り」、第2曲は「白い月影は」。
まっ、私はぐっすり眠ったけど……
シャーリー=カークのバリトン、アンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏を。
1980年録音。グラモフォン。
昨日の昼は、天気が良かったせいもあって秋吉課長と大嵐係長と連れ立って久しぶりに珍宝楼に行き、“いつもの”担担麺+小ライスを食べた。
おいひかっふぁ!
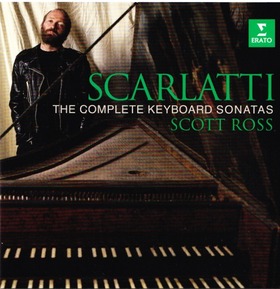 聴くチャンスは少ないかもしれませんが……
聴くチャンスは少ないかもしれませんが……スカルラッティ(Domenico Scarlatti 1685-1757 イタリア)は555曲のソナタを残した(→奇特な人はこちらをご覧ください)。
今日はそのなかのオルガン用のソナタ ニ長調K.288(L.57)。
2分ちょっとの短い曲だが、なんとも魅力的なのだ。
私はオルガンの音栓(ストップ)のことはよく知らないが、バグパイプのような音とリコーダーのような音、そしてオルガンらしい音が呼応しあって色合い豊かに楽しげなメロディーを奏でる。
なかなか耳にする機会はないかもしれないが、私はけっこう気に入っている。
ロスのオルガンで。
1984-85年録音。エラート。
スカルラッティのソナタの全曲盤である。
 ティッシュ片手に……
ティッシュ片手に……話は曲と全然関係ないが、先日ロートの“デジアイ”という目薬を買った。
容器の色が黄色いのかと思ったら、薬自体も黄色。
衣服なんかに着くとシミになることがあるので注意するように書かれている。
私は目薬をさすのがとっても下手だ。
左手でまぶたが閉じないよう押さえつけなきゃとても目を開いてられないし、なぜか3回に1回は液が的である瞳から外れる。
つまり製品容量の12mlのうち4mlはロスしていることになるのだが、それよりなにより今回の場合はこのテントウムシのゲロのような色が服に付着してしまう可能性がとても高いのだ。
やれやれ……
目薬をさすたびに極度の緊張を強いられている。
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
- J.S.バッハ
- JR・鉄道
- お出かけ・旅行
- オルガン曲
- オーディオ
- カップ麺・カップスープ
- ガーデニング
- クラシック音楽
- コンサート・レビュー
- コンビニ弁当・実用系弁当
- サボテン・多肉植物・観葉植物
- シュニトケ
- シューマン
- ショスタコーヴィチ
- ストラヴィンスキー
- スパムメール
- セミ・クラシック
- タウンウォッチ
- チェロ協奏作品
- チェンバロ曲
- チャイコフスキー
- ディーリアス
- デパ地下
- ドビュッシー
- ノスタルジー
- ハイドン
- バラ
- バルトーク
- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽
- バロック
- パソコン・インターネット
- ピアノ協奏作品
- ピアノ曲
- ブラームス
- ブリテン
- ブルックナー
- プロコフィエフ
- ベルリオーズ
- ベートーヴェン
- マスコミ・メディア
- マーラー
- ミニマル・ミュージック
- モーツァルト
- ラヴェル
- ラーメン
- リッピング
- ルネサンス音楽
- レスピーギ
- ロシア国民楽派
- ロマン派・ロマン主義
- ヴァイオリン協奏作品
- 三浦綾子
- 世の中の出来事
- 交友関係
- 交響詩
- 伊福部昭
- 健康・医療・病気
- 出張・旅行・お出かけ
- 前古典派
- 北海道
- 印象主義
- 原始主義
- 古典派・古典主義
- 合唱曲
- 吉松隆
- 国民楽派・民族主義
- 変奏曲
- 大阪・関西
- 宗教音楽
- 害虫・害獣
- 家電製品
- 岩石・鉱物
- 広告・宣伝
- 弦楽合奏曲
- 手料理
- 料理・飲食・食材・惣菜
- 新古典主義
- 映画音楽
- 暮しの情景(日常)
- 本・雑誌
- 札幌
- 札幌交響楽団(札響・SSO)
- 村上春樹
- 歌劇・楽劇
- 歌曲
- 江別
- 演奏会パンフレット
- 演奏会用序曲
- 特撮映画音楽
- 現代音楽・前衛音楽
- 空虚記事(実質休載)
- 組曲
- 編曲作品
- 舞踏音楽(ワルツ他)
- 蕎麦
- 行進曲
- 西欧派・折衷派
- 読後充実度
- 邦人作品
- 駅弁・空弁
© 2014 「新・読後充実度 84ppm のお話」