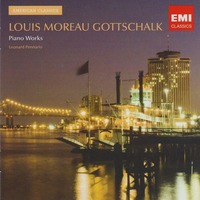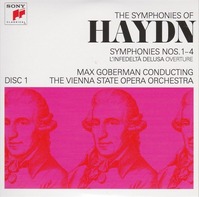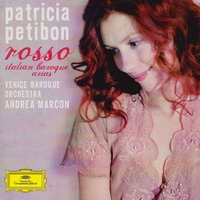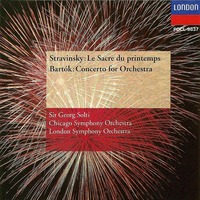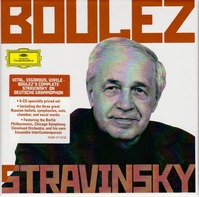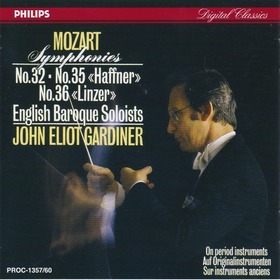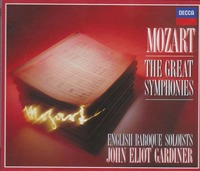シューーーートッ!
シューーーートッ!
月曜日。
朝目覚めてカーテンを開けると(棚ではなく窓の)、外はまだ真っ黒黒べえのような闇状態で、あらゆるものがウスターソースにまみれたアリのように判別しにくかったが、それでも夜のうちに雪が積もったことはわかった。
そしてまた、夜中に寝ぼけて(きっと全盛期のベッカムになった夢をみたのだろう)湯たんぽを蹴ってしまい、右足の小指がけっこう痛かった。
働くおじいさんは「雨だ」と言った
6時前。空がやや明るくなってきたので、この明るさならおやぢ狩りに遭うこともないだろうと、パンパンに膨らんだゴミ袋を携えて新聞を取りに行った。
なぜ新聞を取りに行くのにゴミ袋、それもパンパンに膨らんだものを持参したのかというと、月曜日は“燃やせるゴミの日”だからだ。
外に出ると確かに雪が積もっていた。5cmくらいだろうか。しかも重そうな雪だ。
キュッキュッと雪を踏みしめながらゴミステーションに行くと、なんとそこではおじいさんが柴刈り、いや、雪かきをしていた。
この人、よく見かける。
私はなぜか不思議とよく遭遇する。
このマンションに住んでいる人だ。
きっと趣味ではなく、何らかの対価と引き換えに管理人的な仕事を請け負っているのだろう。仕事だから、おやじ狩りや振り込め詐欺やコンビニ強盗やレイプ魔なんかちっとも怖くないって態度、というか管理業務以外のことには一切無関心というオーラを放ちながら、暗いうちからつまらなそうに雪かきをしていたのだ。
私は礼儀正しいのでちゃんと挨拶をする。
「おはようございます」
「いま何時だと思ってるのかね?ゴミを出すのが早すぎる!」と言いがかりをつけられないか内心びくびくである。
しかしおじいさんは作業の手を止めず、私の方を見ようともせずに「雨だ」と言った。
どうも噛みあっていない気がするが、いや全然会話になっていないのは明白だが、このおじいさん、予言者なんかじゃなく、確かに小雨が降ってきた。
火の気、無し
重くてやや深い雪のせいで朝の通勤時は歩きにくかった。
しかし、日中は気温がどんどん上がり、昼食どきは歩道がべちゃべちゃだった。
にもかかわらず、陽気に誘われて私と秋吉課長と阿古屋係長は、秋吉課長の提案で〇〇楼よりはやや遠い串揚げの店“つのかくし”(仮名)に行ってみることにした。
この店、大阪の串揚げを気軽に、というようなコンセプトだったはずだ。
以前はランチもやっていたが、その後は夜のみの営業になり、そしてまた数か月前からランチ営業を復活させたという、私なんかには事情はわからないが、どうも自ずから客の定着を拒絶しているような振る舞いをしているように思えてならない。
数週間前の金曜日。寒いにもかかわらずやはりこの3人で行ってみたところ、“金曜定休”と出ていて、当たり前のごとく店の戸は固く閉ざされ、中に人の気配がまったくしなかった。
やれやれ。よりによって定休日に来てしまったわいと、なぜ金曜日が定休日なのか疑問は残ったものの、そんなの相手の勝手だから恨んでもしょうがない。私たちは別な店に行って生姜焼き定食を食べた。
こう書いていて気づいたが、私はしょっちゅう生姜焼きを食べているような気がする。
月曜日は店に向かう途中で、早くも私と課長とはメンチカツ定食にしようと心に決めていた。
あの金曜日のときに、ひと気のない店のガラス戸に貼ってあった写真つきランチメニューをチェックしておいたのだ。
しかし、阿古屋係長が心に秘めていたメニューはわからなかった。
あと1本道路を渡ればゴールだ!
しかしそのとき、私はなんとも嫌ぁ~な気持ちになった。
なんとなく建物に生体反応を感じないのだ。店内の照明が灯っている様子もない。
生体反応がなく照明も灯ってないとしたら、それは薄暗い留守宅だ。
入口まで行くと、ほらほら“臨時休業”の張り紙が!
臨時休業というくらいだから臨時で休まなきゃならないようなことが起こったのだろう。
それにしても、2度続けて拒絶されてしまった。
「2度あることは3度ある」とも言う。私たちはこの店に縁がないのだろうか。
そしてやっぱりこの店、客が定着するのを前向きに拒絶しているように思えてならない。
難しい選択だったようで……
この反動を受け、私たちは1丁ほど戻り、出前一丁とは関係ないがラーメン屋に入った。
この店はいつも混んでいる人気店なのだが、幸運なことにたまたま席が空いていた。絶望の世界から希望の惑星にたどり着いた気分だ。
私「みそラーメン」
秋吉課長「みそラーメン」
阿古屋係長「う~ん……、どうしようかな……え~と」
係長は、頭の中で「生きるために食べよ、食べるために生きるな」というソクラテスの言葉が頭の中に渦巻く哲学者のように、目を閉じ、天を仰ぎ、そして目を見開き、注文を取りに来た顔立ちが美しく人当たりの良い店員女性に対して出発信号を指差確認する運転士のように指を差し、これぞ究極の選択とばかりに力を込めて言った。
「みそラーメン!」
この女性(おそらくこの店の若奥さんだろう)は、しかし動揺することも無く「みそラーメン3つですね」と反復しただけだった。私としてはここで「しょう油チャーシュー大盛り、白ねぎ&煮玉子トッピング」あたりを期待していたのだが……
これはまたマニアックな編成だこと……
ハイドン(Franz Joseph Haydn 1732-1809 オーストリア)の交響曲第22番変ホ長調Hob.Ⅰ-22「哲学者(Der Philosoph)」(1764)。
「哲学者」のニックネームはハイドン存命中にすでについていたというが(だからハイドンもたぶん知っていただろう)、その由来は不明。
この交響曲は編成が変わっていて通常なら2本用いられるオーボエの替わりに2本のコーラングレが用いられている。
コーラングレはオーボエの仲間の楽器だが、音域がオーボエより低い。
そのためオーボエよりも音色が渋い(コーラングレが奏でるメロディーで有名なものにドヴォルザークの「新世界交響曲」の第2楽章(家路)がある)。
ハイドンがどのような狙いでこのような特殊な編成にしたのかわからないが、「哲学者」の由来は、コーラングレの渋い音→思慮深そう→哲学者っぽい、ってところかもしれない。
が、渋いことは渋いが、第1楽章なんかはボャ~ンとして締まりがない感じがしないでもない。
哲学者ってこんなに気が緩々してるのか?
私としてはこの曲に、「哲学者」じゃなくて「藪医者」とでもつけたいところだ。
で、時代も国も違うけど、第1楽章冒頭はエルガーの交響曲第1番のそれを思い起こさせなくもない。
曲は緩→急→緩(メヌエット)→急の4つの楽章からなる。この形は教会ソナタの形式である。
バグパイプ風のコーラングレの音色の妙味や、楽想的にもなかなか良いところがあるが、でもこの第22番、刺激が足りなくてあくびしちゃいそうにならなくもない。
私がすっかりはまってしまったゴバーマン/ウィーン国立歌劇場管弦楽団の演奏を。
1960-62年録音。ソニークラシカル。
やれやれ。
1週間を振り返ろうとしたら、月曜日だけでこんなに話がくどくなってしまった。
始めは全体の半ばである by プラトン
↑ よく意味わかんないけど